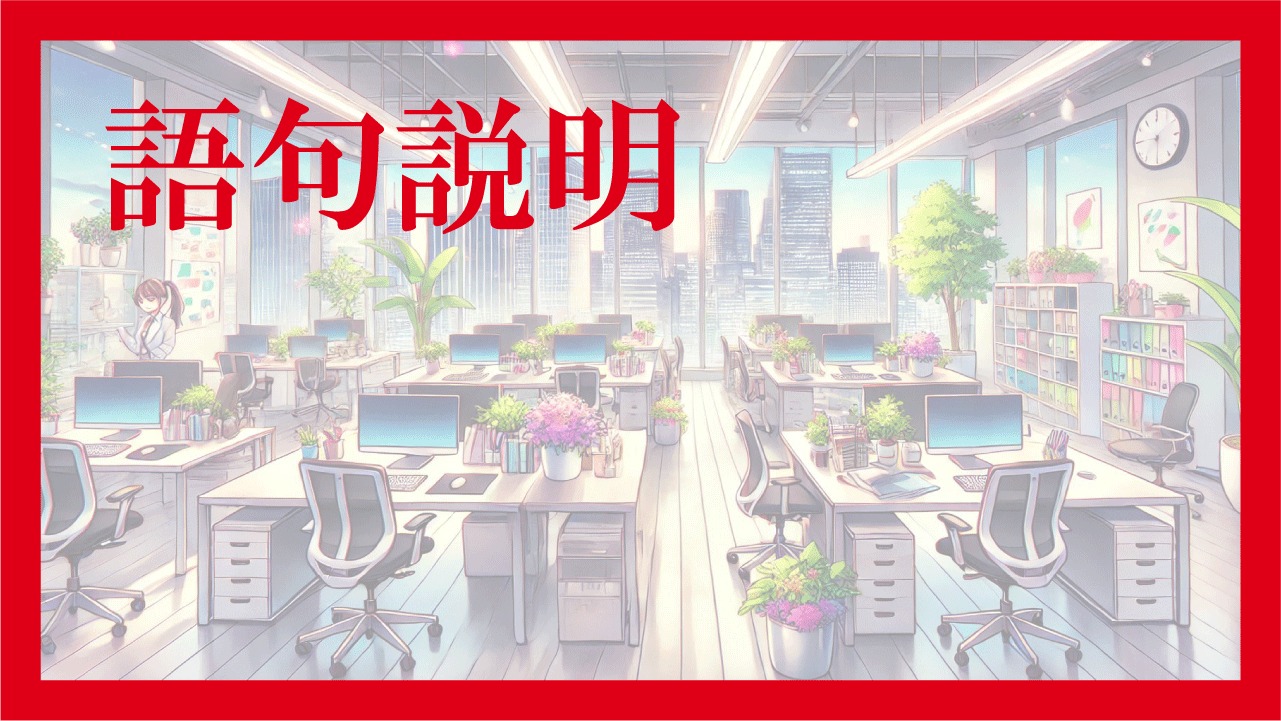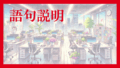民法では、
遺産は相続人に公平に分割されるべき
と考えているようです。
その趣旨を実現するために
特別受益 と 寄与分 という
修正手段が民法には規定されていると考えると 頭を整理しやすいです。
今回はそのうちの 寄与分についてご紹介します。
【寄与分】とは、
被相続人の財産の形成に特別に貢献したと認められた相続人が、
その貢献の度合いに応じた金額を、
法定相続分に加えて受け取れる
という民法に規定されている制度のこと。
※ 制度上、相続人以外の者が寄与分を受け取ることはあり得ない。
具体例)
被相続人には A、B、Cの3人の実子がいて、配偶者は既に亡くなっている。
被相続人の亡くなった時の遺産総額は現金3,000万円。
被相続人が亡くなる20年前から Aは仕事を減らして被相続人を訪問介護していた。
| 寄与分の対象者 | 被相続人の財産の維持または増加に特別に寄与した相続人 |
| 特別の寄与 | Aが被相続人に行っていた介護行為等 |
| 実務上 | 特別の寄与を主張しても 認められづらい。 |
仮に、裁判所が
Aの訪問介護行為を 特別の行為 であり、
その価値を600万円(年間30万円)と認めてくれた場合とそうでない場合を比較してみます。
寄与分と認めてもらえる場合は
Aの行為によって 被相続人の財産の消耗を防げた と考え、
その寄与分の額は 寄与した者が取得できます。
| 寄与が認められない場合 法定分割 | 寄与が認められた場合 法定分割 | |
| A | 1,000万円 | 1,400万円 (= 800 + 600) |
| B | 1,000万円 | 800万円 |
| C | 1,000万円 | 800万円 |
ですので、寄与分が認められた場合は、
まずはその額を遺産総額から控除します。
その結果 遺産総額は 2400万円(=3000 – 600)とみなして分割します。